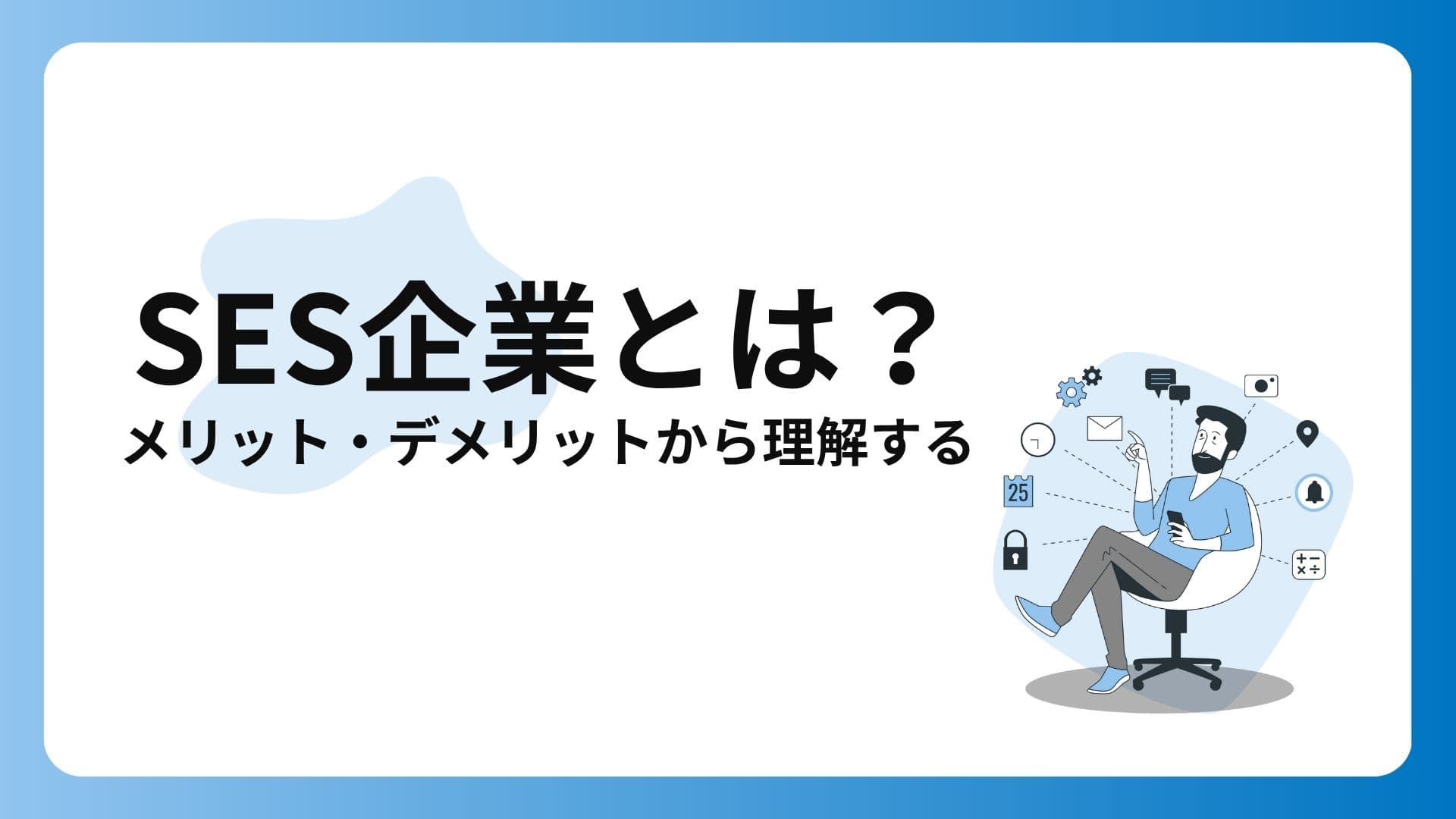SESのキャリア
SESでは案件を選べないって本当?希望のキャリアを諦めないためにエンジニアが取るべき行動
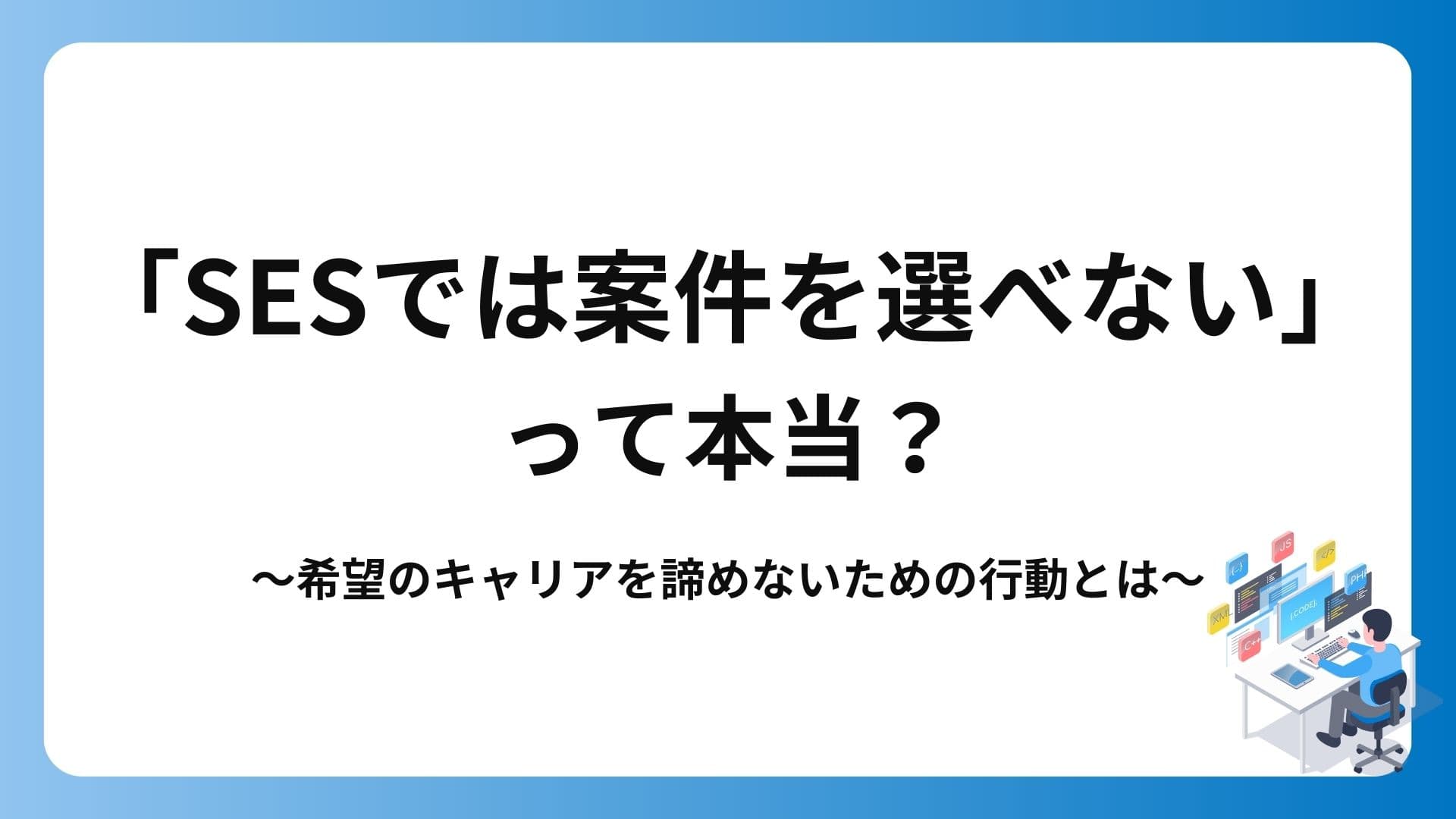
最終更新:2025.11.25
公開:2025.11.07
「SESは案件を選べない」という通説は本当なのか?と不安を感じているエンジニアは少ないでしょう。
まるでガチャのように、運任せでプロジェクトにアサインされる「案件ガチャ」という言葉も生まれ、自分のキャリアプランと合わない案件で疲弊したり、成長が停滞したりするケースも珍しくありません。
しかし、SESだからといって案件を全く選べないわけではなく、希望の案件に参画しているエンジニアも多く存在します。
本記事では、SESで案件を選べない現状の根本的な理由を理解し、その上で、案件選びを「受け身」から「能動的」な活動に変えるためのヒントを解説します。
この記事でわかること
- SESで案件を選べない現状の根本的な理由を理解する
- 希望の案件に参画するために必要な行動を明確化する
- 案件選びを「受け身」から「能動的」な活動に変えるヒントを得る
Necmos編集部
Necmos編集部は、現場で活躍するエンジニアの声やリアルな経験に基づいた信頼性の高い情報を発信し、読者が自身のキャリア形成に役立てられるようサポートしています。 また、エンジニア一人ひとりの価値観や想いを大切にしながら、業界最高水準の給与還元を透明性の高いマージン設計で実現することで、エンジニアが安心してキャリアに集中できる環境を整えています。
「SESは案件を選べない」という通説は本当なのか?その構造的な原因
SESで案件を選べないと言われる背景には、エンジニア自身の問題と業界特有の構造的な原因が複数存在します。
なぜ希望の案件に出会えないのか、その根本的な原因を理解することで、課題解決への糸口が見つかります。
案件選びに影響するエンジニア側の要因
- スキルと市場のミスマッチ
自身の経験やスキルが、市場で求められるニーズと合致していない場合、応募できる案件が少なくなり、希望する案件に巡り合えなくなります。 - 経験・スキル不足による選択肢の狭さ
特に未経験や経験が浅い場合、そもそも応募できる案件が少なく、選択肢が限られてしまいます。
- 希望条件が多すぎる
勤務地、技術スタック、単価など、希望条件が多岐にわたると、案件が絞り込まれすぎてしまい、見つからなくなることもあります。
業界特有の構造的な原因
- 商流の多重化
間に複数の会社(元請け、二次請けなど)が入ることで、エンジニアの希望が発注元に正確に伝わらなかったり、逆に発注元のニーズがエンジニアに伝わりにくくなったりします。
- 営業との連携不足
エンジニアが自身のスキルやキャリアプランを明確に伝えきれていない場合や、営業がそれを十分に理解できていない場合、適切な案件が提案されません。
- 営業担当のインセンティブ構造
営業担当者が個人の成績やインセンティブを優先し、エンジニアの希望よりも契約の取りやすさを重視するため、エンジニアの希望に沿わない案件を勧めることがあります。
- 案件情報の非公開性
公開されている案件情報が少なく、選択肢が限られている現状では、希望に合う案件を探すこと自体が困難です。会社の利益を最優先するあまり、高単価な案件や自社都合の案件を優先的に決定するために、エンジニアに案件情報を公開しない方針を取る企業もあります。
これらの構造的な課題と、エンジニア自身の要因を理解した上で、次に示す具体的な行動を起こすことで、案件選びの状況を改善できる可能性が高まります。
案件獲得のためにエンジニア自身が取り組むべき3つの行動
案件選びを「与えられるもの」ではなく「自分で選ぶもの」というマインドに切り替えることが、希望のキャリアを築く第一歩です。
ここでは、受け身ではなく主体的に案件獲得に向けて取り組むべき、具体的な3つの行動を解説します。
キャリアプランの明確化
漠然と「こういうことがやりたい」と希望を伝えるだけでは、営業担当者も具体的な案件を探しにくいものです。
将来的にどのようなエンジニアになりたいのか、どのようなスキルを身につけていきたいのかを具体的に言語化することで、営業担当者との共通認識が生まれ、ミスマッチを防げます。
- 短期目標:次のプロジェクトで身につけたい技術、経験
- 中期目標:3年後に目指すポジションや役割(例:プロジェクトリーダー、特定の技術領域のスペシャリスト)
- 長期目標:将来的にどのような働き方をしたいか(例:フリーランス、自社サービス開発)
スキルの棚卸しと可視化
自分のスキルや経験を客観的に整理し、営業担当者や面談先の企業に明確に伝えることが重要です。
スキルシートを最新の状態に保つだけでなく、可能であれば個人で開発したポートフォリオやブログ、GitHubなどで成果物を可視化しておきましょう。
これにより、口頭では伝えきれない技術力や熱意をアピールでき、希望案件への参画率が高まります。
営業とのコミュニケーション強化
営業担当者は、あなたの「相棒」とも言える存在です。
希望案件に関する情報収集や、面談後のフィードバックなど、こまめな報連相を通じて、良好な信頼関係を築くことが欠かせません。
営業担当者があなたのキャリアプランやスキルを深く理解すればするほど、より精度の高い案件を提案してくれる可能性が高まります。
これらの行動は一見地道な努力に思えるかもしれませんが、案件選びを能動的に変えるための確実な一歩となります。
それでも解決しない場合は転職も視野に入れる
これまでに挙げたような自己努力を続けても、案件選びの状況が改善しない場合、それは所属している企業の構造そのものに原因がある可能性があります。
商流が複雑すぎる、営業担当者のリソースが不足している、そもそもエンジニアのキャリアを尊重する文化がないなど、個人ではどうにもならない壁にぶつかることも少なくありません。
そのような場合は、案件選択が可能なSES企業への転職を視野に入れることも、キャリアを諦めないための現実的な選択肢となります。
案件選択制を採用している会社の選び方
「案件選択制」をうたうSES企業でも、その実態は様々です。
本当にエンジニアファーストで案件を自由に選べる企業を見極めるために、以下のチェックポイントを確認しましょう。
- 営業担当者との面談(面接): 面接時に、案件選びの具体的なフローや、営業がエンジニアの希望をどこまで尊重してくれるかを確認しましょう。特に「希望しない案件を断った場合にどうなるか(次の提案までの期間や、待機期間中の扱いや給与など)」を具体的に質問するのは、企業のスタンスを見極める上で非常に有効です。
- キャリアプランへの理解度: 案件を選ぶ前提として、あなたの数年後のキャリアプラン(例:PL/PMになりたい、特定の技術を極めたい)を真剣にヒアリングし、理解しようとする姿勢があるかが重要です。面談時に、そのプランに基づいた案件提案の具体例があるかを尋ねてみましょう。
- 口コミや評判: 企業の口コミサイトやSNSで、実際にその企業で働いているエンジニアの声を調べます。「案件ガチャ」を回避できているか、「希望のキャリアを優先してもらえた」「営業のサポートが手厚い」といった具体的な声があるかに注目しましょう。
これらのポイントを事前に確認することで、自己努力が報われる環境を手に入れ、理想のキャリアに近づくことができます。
案件選びの落とし穴と、避けるべきNG行動
案件を自分で選べるようになっても、後悔しないためには注意すべき落とし穴や、避けるべきNG行動があります。
多くのエンジニアが気づかないうちにやってしまいがちな失敗を事前に把握し、成功事例から学びましょう。
案件選びで後悔しないためのNG行動
案件内容をよく確認しない
魅力的な技術スタックや単価だけに目を奪われ、業務内容やチーム構成、開発手法といった詳細な案件情報を十分に確認しないのは危険です。入社後に「思っていたのと違う」と感じる原因になります。
営業にすべてを任せる
案件情報の収集や面談での質問事項など、すべてを営業に丸投げするのはNGです。主体的に情報を集め、疑問点は自ら質問する姿勢がなければ、理想の案件には巡り合えません。
スキルアップを怠る
案件を選べるようになっても、市場価値を維持・向上させる努力を怠れば、再び選択肢が狭まります。常に新しい技術トレンドを追いかけ、継続的に自己研鑽を続けましょう。
失敗事例から学ぶポイント
案件選びに失敗したエンジニアの多くは、「自分のスキルと案件の難易度が合っていなかった」「希望するキャリアパスと無関係な案件を選んでしまった」「単価の高さやリモートワーク等の条件に目を奪われてしまった」といった点を後悔しています。
これらの失敗の根本には、事前の情報収集不足や、自身のキャリアに対する明確なビジョンがないことが挙げられます。
成功事例から学ぶべきポイント
一方、案件選びに成功したエンジニアは、以下の行動を共通して実践しています。
- 徹底した自己分析
自分の得意なこと、苦手なこと、将来の目標を具体的に言語化し、軸をぶらさずに案件を選んでいます。 - 主体的な情報収集
営業任せにせず、自ら積極的に案件の背景やクライアントの情報を調べ、面談で確認すべき点を明確にしています。 - 成長を前提とした選択
短期的な単価の高さだけでなく、その案件を通じて得られるスキルや経験が、長期的なキャリアにどう貢献するかを考えて選択しています。
これらのポイントを実践することで、SESでも「案件ガチャ」に頼ることなく、自らの手で理想のキャリアを築くことが可能になります。
まとめ | SESでも案件は選べる!その鍵は「能動的な行動」にあり
「SESでは案件を選べない」という通説は、エンジニア側の要因や所属企業の構造が絡み合って生まれるものです。
しかし、案件は営業・会社任せではなく、自ら選ぶものという能動的なマインドセットに切り替えることで、理想のキャリアは実現可能です。
そのためには、スキルを可視化し、キャリアプランを明確化すること。
そして、営業担当者と連携を強化することが不可欠です。
これらの行動は、案件選びの成功だけでなく、継続的に市場価値を高めるためのロードマップとなります。
SESでも、主体的に行動することで希望のキャリアを築きましょう。
この記事を書いた人

千賀 勇輝
SENGA YUKI
株式会社Necmos 取締役
2019年株式会社ネオキャリアに新卒入社。450人の新卒から抜擢され、子会社の立ち上げに参画。その後、Web広告企業に転職した後、キャリアコーチングに出会う。過去に転職で悩んだ経験から、コーチングの重要性を痛感し、株式会社Necmosを創業。キャリア伴走型エージェント事業の統括を行い、社員へのキャリアサポートに情熱を注いでいる。
この著者の記事一覧を見る.jpg&w=1920&q=75)


.jpg&w=1920&q=75)